『三淵嘉子と家庭裁判所』
日本初の女性弁護士、初の女性裁判所長であり、家庭裁判所創設にもかかわった三淵嘉子さん。
時代の先駆者の人物像と足跡を描く。

「ただ普通のお嫁さんになる女にはなるな。男と同じように政治でも、経済でも理解できるようになれ。
それには何か専門の仕事を持つための勉強をしなさい。医者になるか弁護士はどうだ」
このお父様が、とても立派。
自分も親として、我が子の可能性を、偏見や常識に囚われて潰さないようにしたい。
そして「血を見るとこわくなっちゃう」からと、医者ではなく、弁護士を選んだ嘉子さん。
それで本当に弁護士になるのだから、かっこいいですよね。
家庭裁判所ができた当時、「戦災孤児」が、全国で123,511人もいたという数字に、心が粟立ちました。
疎開中に両親が亡くなったり、原爆で親を失った「原爆孤児」であったり・・・
12万以上もの子どもが、そんな状況で、盗みや犯罪を犯しながら、なんとか生き延びていた時代。
言葉を失います。
そういった孤児たちの一部は、家庭裁判所に身柄が送られ、親族を探してもらったり、福祉施設や児童相談所に送られたり。
そんなことも、裁判所がやっていたのかと、驚きました。
『こうした旧来の裁判所とは大きく異なる造りは、親しみやすさを感じてもらうためだった。
後には正面玄関にブロンズ像「母子像」も設置された。
戦争で母親の愛を知らない子どもたちの、幸せを願う気持ちが込められている。』
裁くだけが裁判所じゃない。
愛にあふれた場所・組織なのだなと、家庭裁判所に対する見方が変わりました。
それにしても。
『新憲法下で家事審判法の制定に携わり、家庭裁判所の創設にも加わった。
さらに日本の裁判官の代表として、アメリカの家庭裁判所を視察してきたばかり』
にも拘わらず、
最高裁長官を囲む座談会で
「女性の裁判官は女性本来の特性から見て家庭裁判所裁判官がふさわしい」という発言を受けて、
(先輩の私が家庭裁判所にいけば、後輩の女性裁判官が家庭裁判所に送り込まれることになる)と、家庭裁判所をあえて希望せず、東京地方裁判所に移動した三淵さんは、大局を見て身の振り方を考えられる、素晴らしい人ですね。
その後、やはり家庭裁判所の裁判官になるわけですが、『三淵さんがいるから』と、嘉子さんに憧れて東京家裁を希望する女性調査官が出てきたというエピソードには(後輩たちに、女性だからと、自分と同じ轍を踏ませたくないという意志と矛盾してしまったところが皮肉)、思わずにんまりとしてしまいました。
『保護者の来ない少年の多くは、着の身着のままだった。
家庭裁判所から補導委託先の施設に送ろうとしても、替えの下着も持っていない子どもがいた。
裁判所の予算で支給することはできない。
調査官や裁判官が、見かねて自費で下着や洗面道具を買ってあげることも珍しくなかった。』
ひとりの親として、愛情を受けられない子どもたちのエピソードには、胸が痛みます。
そんな子どもたちのために「少年友の会」というボランティア団体を裁判所の中につくり、バザーなどを開催したり、学習支援をしたり・・・
読めば読むほど、家庭裁判所に関わる人たちのエネルギーと愛の深さに、感服してしまいました。
戦災孤児、非行少年(フーテン、ヒッピー、カミナリ族)、学生運動・・・と、時代と共に、向き合う少年少女たちの内容はさまざま。
でも、嘉子さんの中では一貫して、彼ら彼女らを導きたいという、まっすぐなきもちがあった。
「やっぱり、私は、人間を信じているということなのじゃないかな。人間というものを信じている。
だからどんなに悪いと言われている少年でも、少年と話をして審判をしているときに、必ずこの少年は、どこかいいところがあって、良くなるのじゃないかと希望を失わないです」
「信じる力」が、人からの信頼を引き寄せる。
三淵嘉子さんの魅力が、もっとも良く現れた部分だと思いました。
少年法の対象年齢を引き下げるか否か(反対派の裁判所・弁護士vs賛成派の法務省と検察)といった問題、構図も分かりやすく書かれていて。
三淵嘉子という人物以上に、法の世界、戦後の日本の歴史について深く考えさせられた名著でした。
紋佳🐻
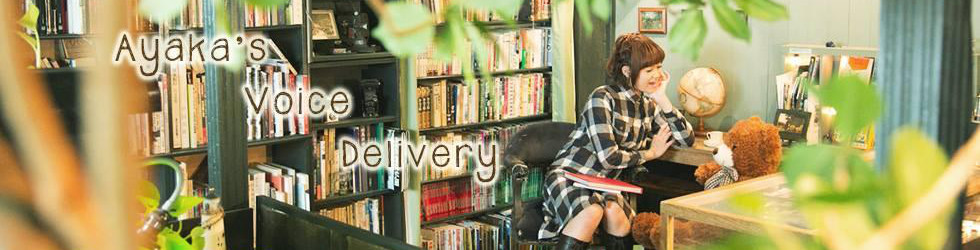








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません