『世界の食卓から社会が見える』
世界各地の家庭に滞在し、その家の人とその土地の食材で料理をして食卓を囲むと、それまで気づかなった疑問が湧いてくる――
・どうしてここのほうれん草は日本のより味が強いんだろう
・肉とチーズを一緒に食べることが宗教的にだめってどういう理屈だろう
・なぜアボカド産地なのにいいアボカドが買えないのだろう
・ブルガリアの人って本当にヨーグルトをたくさん食べるんだろうか
そんな疑問から、食べ物と政治、宗教、環境、教育、気候、民族などとのつながりを解き明かしていく。
台所探検家・岡根谷実里が探る「おいしい/おいしくない」を超えた料理の向こう側の話。

・ブルガリアでヨーグルトが消費されていたのはソ連統治の時代に国策で大量生産・消費させられていた(社会主義的思想)から。
・メキシコのトルティーヤは、メキシコ原産の白いとうもろこしを使った白いものが本物。アメリカからの輸入もろこしが規制をかいくぐって使われ「黄色いトルティーヤ」が流通してしまっており問題になっている。
・コロナ禍で失業し、寮を追い出されたベトナムの技能実習生が、埼玉県のお寺で共同生活を送っている。
(技能実習生のうちの約55%が、母国の送り出し機関に対して支払う平均約66万円に対して借金をしてから来日している)
・ヨーロッパに続いてオーガニック農業が発展しているキューバは、キューバ革命後、アメリカによって禁輸措置をとられたことで、化学肥料・農薬・農耕機のための燃料が手に入らなくなったことにより牛耕へと回帰し、有機農業が発展してきた。
どの話も、初めて知ることばかり。
「食」の話が、宗教・政治・教育・貧困・・・といった社会問題と密に関係しているのだと勉強になりました。
そんなシリアスでセンシティブな話題にも関わらず、わかりやすいように、偏らないようにとの配慮が感じられる岡根谷さんの文章はとても素晴らしく、まだ拝読中にも関わらず、ひとにオススメする私。
読んでいる途中でも誰かに薦めたくなる。
誰かに読んでもらい感想を聞きたくなる。
そんな素晴らしい本でした。
紋佳🐻
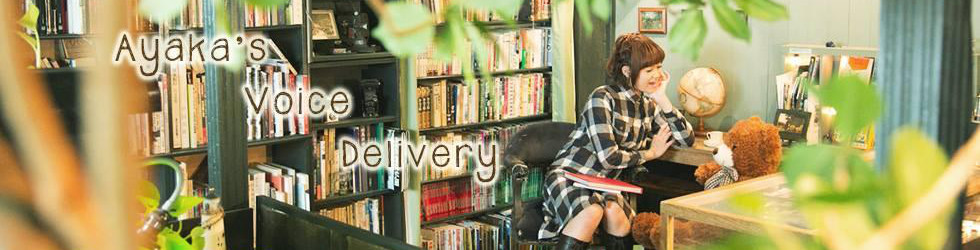


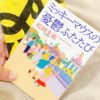





ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません