『紙つなげ!彼らが本の紙を造っている 再生・日本製紙石巻工場』
「この工場が死んだら、日本の出版は終わる・・・」絶望的状況から、奇跡の復興を果たした職人たちの知られざる闘い。
「8号(出版用紙を製造する巨大マシン)が止まるときは、この国の出版が倒れる時です」
2011年3月11日、宮城県石巻市の日本製紙石巻工場は津波に呑みこまれ、完全に機能停止した。
製紙工場には「何があっても絶対に紙を供給し続ける」という出版社との約束がある。
しかし状況は、従業員の誰もが「工場は死んだ」と口にするほど絶望的だった。
にもかかわらず、工場長は半年での復興を宣言。その日から、従業員たちの闘いが始まった。
食料を入手するのも容易ではなく、電気もガスも水道も復旧していない状態での作業は、困難を極めた。
東京の本社営業部と石巻工場の間の意見の対立さえ生まれた。
だが、従業員はみな、工場のため、石巻のため、そして、出版社と本を待つ読者のために力を尽くした。
震災の絶望から、工場の復興までを徹底取材した傑作ノンフィクション。

「ものすごい揺れだったけど、マシンは無事だったし、津波が来るとも思わなかった。
ほかの課の従業員が避難して、自分たちだけ孤立するのも嫌だったんで、みんなで逃げようかということになったんですよ」
「たとえ津波が来ても、チャポチャポって足元が浸かる程度だろうと思いました。」
海から1kmしか離れていない工場で、働き、暮らしている人の防災意識が、このレベルだったことに驚きました。
2003年の宮城県沖地震、2010年のチリ地震で、津波の被害が小さかったせいもあるのだそう。
雪が降っていたせいで、「寒いから上着を取りに戻りたい」そんな油断すらあった地震直後の様子。
そして、大きな津波に飲み込まれていく街、人。
津波が火事を押し広げていくなんて、知りませんでした。
逃げ遅れた人たちの悲鳴、うめき、
さまざまなものが燃えるにおい、
生々しい描写は、偽りも美化もありません。
心と体に傷を負いながらも、従業員1,306名が全員無事だったのは本当に奇跡的です。
紙の流行についてのお話も興味深かった。
『ひと昔前には、光沢があればあるほどいいという時代がありました。
しかし次第にピカピカしすぎるのは品がないという風潮になり、自然な光沢や風合いが好まれるようになったんです。(中略)
また書籍の色にも流行があって、以前はクリーム色がかったものが主流でしたが、ここ数年はホワイト、スーパーホワイトも人気が出てきた。
時代が明るいものを求めているのではないか、と思いますね』
『何年前だったかな、教科書で使われるような青味がかったものがよく出ました。
これはヨーロッパで好まれている色なんですよ。
でもヨーロッパと日本ではやっぱり光の加減も感性も違う。
最近ではナチュラルな方向へ変わりつつあります』
どんな紙が、どんな出版物に合うのか。
思わず、へぇとこぼれるお話も。
紙好きとして、興味津々です!
日本製紙が約630億円かけて投入した最新マシンN6。
比較対象として並べられた東京スカイツリーの総工費は、約650億円だそうで、そんな大切なマシンが津波に襲われただなんて、戦慄ものです。
気が滅入ってどうしようも無い時に、上司が部下を笑わせ、笑うことで少しでも精神力を保とうとする中、「何笑ってるのよ!」と住民から金切り声で叫ばれる。
どちらも、間違っていない。
やるせないこと、この上ないですね。
巻末の「震災直後」と「復興後」の比較写真(工場内)たちにも圧倒されました。
ひとってすごい。
たくさんの人の人生が、そこにはありました。
紙業界、出版業界を支えてくださって、ありがとうございます。
紋佳🐻
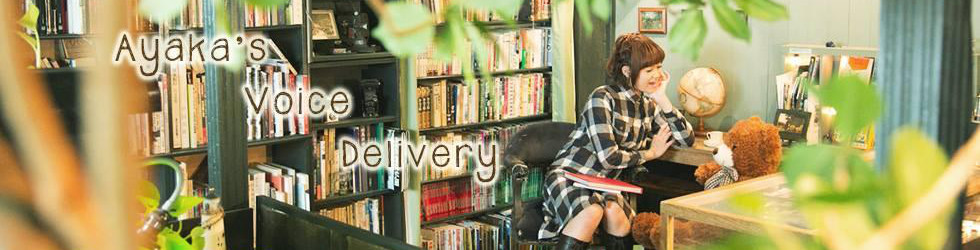








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません