『ふたりの証拠』
戦争は終わった。
過酷な時代を生き延びた双子の兄弟の一人は国境を越えて向こうの国へ。
一人はおばあちゃんの家がある故国に留まり、別れた兄弟のために手記を書き続ける。
強烈な印象を残した『悪童日記』の続篇。
主人公と彼を取り巻く多彩な人物を通して、愛と絶望の深さをどこまでも透明に描いて共感を呼ぶ。

双子の幸せを願うあまり、夢中で読みました。
戦後の国政の混乱、貧しい中でも寄り添い暮らす人々・・・
縁あって父親になった、その後の展開にも驚かされたのに、ラストの衝撃ときたら。
続きが気になるってこういうこと、という終わり方でした。
また、アゴタさんの生涯について語られている解説すらも、物語のようでした。
『一九五六年、ハンガリー動乱。アゴータの夫は反体制の活動をしていた。(略)
ソ連の戦車の介入で「暴動」が鎮圧され、状況が「正常化」するまでのあいだに、約二十万のハンガリー人が、封鎖の解かれていた国境を越えて西側へ脱出した。そのなかに、アーゴタと彼女の夫も混じっていた。
生後四ヶ月の乳飲み子を抱えての逃避行だった。』
生後四ヶ月の子どもを連れての越境。
この時点で凄まじい。
『片言のフランス語も話せない妻は、ふたたび女工となって時計工場で働く。
夢に見た自由の天地の現実は厳しかった。
ここでもまた、夕方になると託児所へ子供を迎えに行く日々。
極端に切り詰めた生活。住まいは、石炭ストーブしかない二部屋。浴室も付いていない。
ひっきりなしの機械音の中で早いピッチの労働に服する彼女に、新しい言語を学ぶ余裕は到底ない。二十五歳。
自作の詩を、ハンガリーからの亡命者仲間がパリで出していた同人誌に発表。』
過酷な労働条件、休まらない住居環境、離婚と再婚と出産、のちの大学進学。
アゴタさんの生涯が物語のよう・・・
もとい、フィクションであってほしいと願わずにいられないほどの波瀾万丈ぶり。
出版された当時の評価は、以下の通り。
『若い世代では、まず高野亘氏が《朝日ジャーナル》の読書日記欄で、「いや、まいりました」とA・クリストフに脱帽された。
江國香織氏も、《婦人公論》の同様の欄によれば、『悪童日記』に「我を忘れて熱中し、子供の頃の読書を思い出」されたらしい。
また最近では、これは特筆しておきたいのだが、あの塩野七生氏が、出版後半年以上を経た時点で同書を発見されたらしく、「読後感は震駭(ふるえおどろくこと)の一語につきる」と絶賛したうえ、「続篇を一日も早く読みたい」と、連載中のある書評コラムに書いておられる。』
全く存じ上げなかったことが、恥ずかしくなる程の評価、話題だったのですね。
『いっさいの説明や感情移入や修飾を省いた「白い」文体である。』
そのような、簡素で端的な文章だから、一文と一文の間に、劇的な変化が突然起こっていたりする。
そこに登場人物や読者の感情はない。
ただ、歴史が動いていくだけ。
そんな惨さがびしりびしりと伝わってくる作品。
第二作目も、頬に張り手を喰らわされたような痺れをもって、読了です。
紋佳🐻
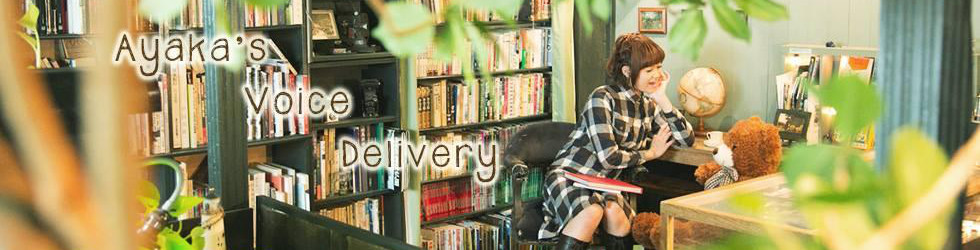








ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません